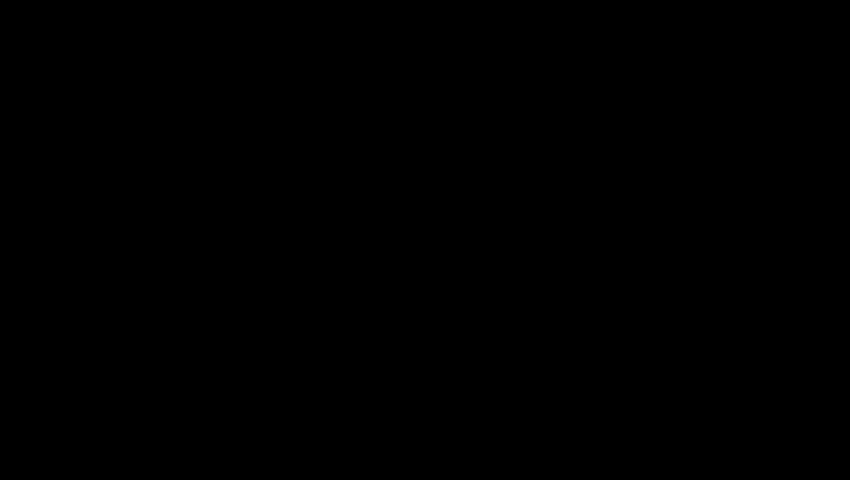同志社人インタビュー第14回 ~株式会社八代目儀兵衛 橋本 儀兵衛 (隆志) さん~
同志社人インタビュー第14回目は、前回の梶川由紀さんにご紹介いただいた、株式会社八代目儀兵衛 橋本 儀兵衛さんにインタビューを行いました。
米料亭「八代目儀兵衛」の祇園店を訪問させていただき、貴重なお話を沢山お伺いすることができました。
ぜひ最後までご覧ください!

(米料亭「八代目儀兵衛」祇園店にて)
橋本 儀兵衛(隆志)氏 株式会社八代目儀兵衛 代表取締役CEO
1995年同志社大学商学部卒業
インタビュアー ・同志社高等学校3年生 竹村 華(写真:右)
・同志社大学政策学部 政策学科 3年次生 村元 柚月(写真:左)
Q.いろいろなお店やレストランにお米を卸されていて、お店やお料理ごとにお米の品種・ブレンドが異なるとのことですが、どのような違いがあるのですか?
A.みなさんが日常的に食べる米というのは、品種で販売されることが多いです。
同じ品種でも産地や農法によって違いがあります。でも、ほとんどの人たちはその違いを知らない。わたしたちは、お米を全国から仕入れ、たくさんの産地・品種の味や特長を知っています。料理別の相性や違いから言うと、粘りと食感が一番大きい。和食でぱさぱさのご飯が出てきたら美味しく感じない。お寿司屋さんで粘り気の強いお米が出てきたら上手く握れないうえに、ご飯が口の中に残ってしまう。中華料理の炒飯も同じように、炒めたら団子状態になったりだとか。料理の用途に合わせてお米の粘り気や食感を変えることが出来るのが、私たちの技術。全国のお米からチョイスしてブレンドするというのが売りになっています。ブレンドという行為は、お米をより味わい深くしたり、食感を用途に合わせられたりする、要はテクニックなんです。そのノウハウを、僕たちは日々研究しています。だからこそお店にノウハウを提供すれば、お客さんにはより質の高いご飯を味わってもらえる。それを私たちは売りにしています。
Q.八代目儀兵衛様では、お米の目利きや精米、ブレンドを担当されている橋本儀兵衛様と、選び抜かれたお米を炊き上げる橋本晃治様のご兄弟で事業を展開されていると伺っております。ご兄弟でお仕事をご一緒にされているからこそ発揮できる強みや、連携におけるメリットなどはありますか。
A.飲食業をお米屋が経営しているというのは、全国的にも珍しいと思います。
まず、お米を仕入れて精米して配達するというのがお米屋における従来の流通で、お米屋は届けるまでが仕事でした。でもその仕事って誰でもできてしまうし、差別化ができるものでもない。お米の味や食感といった価値をいろんな形でお客さんに伝えていくためには、自分たちが「お米」の状態だけではなく「ご飯」の状態も知ったうえでないと正確に価値が伝わらないと考えました。そこで、従来のお米屋としてだけではなく、「ご飯」を体験できる飲食店を作ろうと考えました。いざお店を開くことを考えたときに、「自分より弟の方が適任なのではないか」と思ったんです。飲食業に携わっていた弟に、「俺がお米を目利きしてブレンドするから、お前はそのお米を極上のご飯としてお客さんに提供する責任者になってくれ」と声をかけました。それが2012年。弟は店舗運営の経験はなかったし料理人という立場で、僕が経営は全面的にサポートするという形でお店を始めました。最初はクレームだらけでした。お客さんに怒られたり、テレビ取材が来て大反響となったこと、でお客さんを長時間待たせてしまったり。そんな色んなことを経験したからこそ強くなれて、本当の繁盛店になっていったのかなと。
兄弟だからこその強みとしては、やはり1番はこういった困難に直面したときに、乗り越えられる意地があることかなと。もしこれが他の人とだったらやめてしまってるかもしれない。それぐらい精神的にきつかったし、元々飲食店のプロとしてやっていたわけではなかったので。そんな状況でも兄弟としての意地で継続していけたというのが、兄弟ならではの強みだったと思います。テレビ局の関係者の方々からは、「お米屋ブラザーズ」と呼ばれたりもして。そのキャッチーな言葉が一人歩きして定着した時には、兄弟でやっていてよかったと思いましたね。
Q.お米を通じた感動体験の提供がビジョンの一要素であると伺いました。普段お米をあまり食べない所謂「お米離れ」の状態にある日本人が多いという現状がある中で、そんな人々に「食」を通じた感動体験をしてもらうためのアプローチ方法や工夫について教えてください。
A.例えば、子ども達へ食育授業をする機会があった時に、よく耳にするのは「お米には味が無い」という声。普段食べているお米は、味がしないと思っている。だから、ふりかけがないと食べられないし、そもそもお米がどういう味をしているか分からない。本来のお米の味を伝えていかないと、パンや麺など代替品がある中で、わざわざお米を選んで炊いて食べるメリットが無いという状況になってしまっています。
実は僕自身も、「お米は主食ではない」と思っています。だからこそお米を、選択して食べるものにしていきたいんです。そのためには、本物の甘いお米を美味しいご飯として提供しなければいけません。しかし、これまでのお米屋は「ご飯としての価値」を今まで提供してきませんでした。
お米のプロとして、お客さんに種類や炊き方にもこだわった唯一無二のご飯を提供すれば、「ご飯ってこんなに美味しかったんだ」と感動してもらえる。その体験をしてもらうために、米料亭「八代目儀兵衛」というお店が存在しているんです。飲食店経営というよりは、お米の価値をお客さんに伝えるための場所。これがこの会社の大きな軸となっています。
また、飲食店や業務卸だけではなく、一般の消費者にもお米をギフトとして販売しています。用途に合わせたお米を使うことで、日々の生活が楽しくなり、お米に対する新しい価値観が生まれます。いつもとは違うお米を提供することで、お米を食べるという一見日常的なことを、非日常の特別な体験として提供し、違った感覚でお米を捉えていただくのが会社の役割の一つでもあります。
世の中の多様化が進む中で、従来とは全く違う考え方はやはり注目を浴びます。しかし、一過性のものにするのではなく本物を追究してきた結果、20年目になる今もこのスタンスを続けることができているのかなと思います。
Q.お米離れを減らしていくために、学生の私たちにも何か出来ることはありますか?
A.まず、お米を炊くという行動からですね。今は家に炊飯器が無い人も多いですが、学生のうちに、研ぐところから炊くところまで自分で仕上げた、美味しいご飯を食べていただいて味を知ってもらうのが良いと思います。やはり日本人にとってはお米は切り離せないものだと思うので、そうすることで、いざ海外に行って「お米ってどんなの?」と聞かれたときに明確に答えられるように、自分でお米を炊いて食べてみるということを是非していただきたいです。
Q.「世界中にごはんの美味しさを広げる」というミッションを掲げられる中で、その達成のためには専門的な技術や深い知識が不可欠であると思います。それらの技能は、どのような体験や修練により培われているのでしょうか。中でも、お米の価値を見極める能力を会得するために大切にされている習慣や価値観があれば教えてください。
A.地味なことですが基本として、社員全員でご飯を食べ続けています。商品であるお米を必ず自分たちで食べて確認して、美味しさを常に追究しています。一般家庭用のものから企業などいわゆる業務用のものまで、どうしたら美味しく炊飯できるのかを、コンサルティングできるレベルまで深く知り尽くしている社員を養成しています。それによって、「お米のことなら」という段階を超えて「ご飯のことなら」という領域までもカバーできる会社になっています。そこから香港など海外企業から声をかけていただいたりもします。日本のお米文化やご飯文化を海外に発信するには、単純にお米を卸すだけでは何も伝わらないということが分かっているので、美味しいご飯の炊き方までを海外に伝えなければいけない。そのためにはまず日本国内で徹底して美味しいお米の食べ方を広げていかなければいけないと思っています。
また、物事を深く掘り下げて考えるということを常に社内で行っています。今の時代、何でも浅く広く見ないと時代に追いつけないということがありますが、私たちは逆に1つの商品を深く分析して、そこに答えを見出そうとしています。僕の座右の銘が「神は細部に宿る」というものなんですが、細部まで掘り下げて物事を考えていけば、人と違う視点が見えてくる。それがビジネスになると私は考えています。
Q.仕事のやりがいを感じる時、仕事が楽しいと感じる時はどのような時ですか?
A.大切にしている、唯一無二の価値観が評価されたときにはやりがいを感じます。自分たちの考えが間違っていたら誰にも相手されないだろうし、今のこの会社はない。例え世間に認められなくても、自分の考えは絶対に間違っていないという、変な自信がありました。でもやはり、実際に評価されたら非常に嬉しいですね。最初に評価されたのは、ANAさんのファーストクラスの機内食に採用されたとき。これは2010年くらいだったと思うんですけど、それがきっかけで色んな企業さんに声をかけていただいて、評価していただいて。1番大きかったのはセブン–イレブンさんかな。自分の価値観やブレンドへの考え方が社会的に評価されて、最終的には企業やお店の売り上げに繋がるという点が、やはりとても嬉しいですね。ブレンドという唯一無二のものを評価してもらうときに、何物にも代えがたい喜びが得られます。
Q.橋本様が、これからお米を通じて起こしたいイノベーションや社会の変化について詳しく教えてください。
A.ここ20数年で、お米がこれほど注目されているのは初めてで、これからどういう風になっていくか全く分からないという状況です。そもそもお米はコモディティと呼ばれていて、言わば水のように、どこにでもある、人々が特に気にしないものでした。そのコモディティをいかに差別化するかという点に着眼していたんですが、徐々にお米はコモディティから資源になって来ています。今は歴史的に大きな転換期に来ていると考えていいでしょう。そんな中で、これまで新しい考え・価値観を発信してきたからこそ、次の世代へも発信をしていかなければなりません。その内容の最たるものが、新しい米づくりです。近年、日本の米農業の形態が問題になっています。乾田直播という、いわゆる田植えをしない米作りのスタイルなのですが、そうすると手間は10分の1に減ります。しかし、この形態で作られたお米は、量は確保できるものの、味の観点はスルーされてしまいがちです。そこで、僕たちが「美味しさ」の観点から企業さんに入り込んでサポートし、量を維持しつつも美味しさを担保できるような日本の米農業にしたいという、大きな野望があります。
Q.大学時代は、どのように過ごされていましたか。学業や、サークルなどの課外活動における過ごし方を教えてください。
A.今回の取材をご紹介いただいた梶川さんと同じく、部外連所属のルナティックススキークラブで競技スキーをしていました。週3回練習があって、上下関係も厳しく冬場になると長い合宿が続くので、そういったバリバリ体育会系のノリにはずいぶんやられましたね。当時はスキーをやりたいから我慢してたけど、そこを体験したからこそ、今この粘り強さがあるのかもしれないですね。
一つのことをやり続けるとか、人前で何かを見せるという時に、「なんでこんなことをしなければならないんだろう」と思うことも多々あったり。だけど、どこかで吹っ切れるんですよ。「死ななかったらいいかな」と思うくらい。そう思う強さはできたかなと。あとはやはり、人と深くお付き合いすると色んな話ができますから、それが人生のなかでも思い出になりましたね。うちの会社に人事コンサルに来てもらっているのはその時(スキー)の同級生です。深く知っているからこそ、その人の言葉を信用できるというのはありますね。
(アメリカへ短期留学した時、現地で仲良くなった友人達とグランドキャニオンに行ってセスナ機に乗った時の写真)
Q.同志社大学で過ごした中で、印象に残っている出来事はありますか?
A.ありきたりの学生生活を送っていましたが、だんだん飽きてきて早く社会に出たいなと思っていました。親の教育方針で、友達を作っておきなさいというのを言われていたので、それは大きかったですね。
Q.学生時代のあの時があったから今がある、というような経験はありますか?
A.入社式で新入社員たちに、”守破離”という言葉をいつも伝えるんですよ。基本を忠実に守り、その次は、基本を破って工夫する、最後には基本から離れて独自の境地へ、ということなんですが、社会に出たときには絶対に下の立場から始まりますよね。そこで色々理不尽な思いを抱くことがあると思います。でも、社会に出た人は、下の立場がどういうものかを理解して、守破離の段階を踏めた人から早く出世していくんですよ。先輩から可愛がられる方法を知っている子たちは、年上の人を何とも思わない強さを持っています。若くて成功するには、能力だけでなく、そういった人間力も養成していく必要があるのではないかなと思います。能力で勝てないとき、最後は人間力で戦うしかないと。
そういう意味でも、1年生の時にスキーの同好会で人との接し方を先輩から鍛えられたのは、社会人になっても活きています。
人間力というのは、イコール感性だと思っています。京都という街では、寺とか神社とか風光明媚なものに囲まれながら学生生活を4年間過ごせますよね。東京ではできない古い建物や紅葉を見て綺麗だなとか、着物を着て街中を歩くとか。文化風習が日常にあるのが京都の街。文化的要素を交えた京都という場所が、人間力を養ってくれているんじゃないかと感じますね。
(大学4年にアメリカ旅行した時の写真)
Q.学生の時に身についた考え方や価値観が、今の事業に影響していると感じる場面はありますか。
A.学生の時に培った価値観の中で今の事業に色濃く出ているものは、「唯一無二」という考え方を継続して大切にしていることです。人と被る必要はない、かといって人と比較ばかりするんじゃなくて、自分でどう人生を創っていくかが大事だと思います。「固有性・オリジナリティを大切に」ということを、これからの方には意識してほしいですね。
Q.学生時代に戻れるとしたら、どのような経験をしておきたいですか?もし学生のうちにやっておいた方がよいことがあれば、教えてください。
A.長期の留学やインターンシップを一度は経験しておきたかったですね。一か所にとどまらず、世界中を実際に見て回れたら良かったと感じることがあります。学生にとって「長期で何かに取り組むこと」はメリットが非常に大きいです。社会人になったあとは、長期で行動するためには仕事を辞めるなど大きな決断が必要になってしまいますから。
特に、短期間の体験よりも、1年間など長期間企業に関わる中で、人間関係や仕事について学ぶことに大きな価値があると思っています。そういう学生が、東京には山ほどいます。学生のうちにしかできないことはたくさんあると思う。新しい環境に飛び込み、半年や年単位という長期間続けてみるという体験は、同志社の学生の皆さんも、ぜひ今のうちにしておいてほしいですね。
Q.(最後に)橋本様にとって同志社とはどのような存在ですか。後輩である同志社大学の学生へ向けて、メッセージをお願いします。
A.同志社大学はリベラルアーツの概念のもと、自由の中で自分のしたいことを見つめることができる学校だと思います。だからこそ変な枠にとらわれず、学生の間に東京とか海外に行って色んな人と交流して、自分の世界を広げてほしいです。過去には、大企業に勤めることが人生のゴールみたいになっていた時代もありましたが、今は決してそうではないので。自分のしたいことを見つけるために有意義な学生生活を過ごしてほしいと思います。
インタビューを終えての感想
■村元 柚月さん(同志社大学政策学部政策学科 3年次生)
橋本様へのインタビューの中で、お米というものが、当たり前にある「コモディティ」から「資源」となりつつある今、私たちは大きな”転換期”にいるのだと実感しました。お米の新しい価値観の提供・それに向けた取り組みについてのお話は、私自身のお米との向き合い方や、学生生活の過ごし方を考える契機となりました。中でも印象的だったのは、「美味しいご飯を世界中の人々に食べてほしい」という思いのもと、深い分析や試行錯誤を重ねて唯一無二を追求される橋本様の姿勢です。用途にあったお米を提供するブレンドへの強いこだわりが、八代目儀兵衛さんの独自の価値を形作っていることに感銘を受けると共に、一貫して独自の価値を突き詰めようとすることの大切さを窺い知ることが出来たと感じています。
今回のお話をお聴きして、京都や同志社という環境でしかできない体験を通して自分のしたいことを見つめ、既存の枠に囚われず後悔の無い学生生活を送っていきたいと強く思いました。
■竹村 華さん(同志社高等学校 3年生)
八代目儀兵衛様にインタビューさせていただき、私は、お米を食してもらうための工夫や、お米離れについての考えなどをうかがいました。
特に印象に残ったのは、「お米離れの状態にある日本人が多い中での工夫」についてのお話でした。橋本様は、日本人が改めて主食としてお米を選んでくれるように、美味しいお米を提供し、そのお米に感動してもらえるように努めているとお話しされていました。新しいお米の価値観や京都らしさをお客様に提供して、日常のお米を特別な体験に変化させているとのことでした。ただお米を売るだけでなく、さまざまな工夫を凝らしながら、日本の食文化をささえているのだと感じました。
また、橋本様には、お米離れを減らすために学生の私たちにも何かできる事があるか、教えていただきました。まずは自分でお米をといで、炊くようにすることが大切とのことでした。日本人にとって、お米は欠かせないものであるはずなので、海外でもその大切さを伝えることができるようにする必要があるそうです。
私の身の回りでも、最近はパンや麺が好まれることが多くなってきています。そうした中で、お米の魅力や八代目儀兵衛様の努力を知ることができ、とても良い学びになりました。私自身も、橋本様に教えていただいたように、普段何気なく食べているお米をもっと「美味しい」ことを意識して食べたり、家族や友人にもお米の良さを伝えていきたいと思います。
お忙しい中、丁寧にお話ししてくださった橋本様にとても感謝しています。
【橋本さんから次回の同志社人インタビューに登場してくださる方をご紹介いただけないでしょうか。】
株式会社名高精工所 代表取締役社長 名高新悟さんをご紹介させていただきます。
彼は叔父さんに有名な俳優 名高達男さんがいらっしゃいます。彼自身も大学卒業後、サラリーマンを経て太くて甘いボイスを活かし、バンドマンとして東京で活躍していたそうです。帰京後は家業のモノづくりの会社を継ぎ、持ち前の人付き合いの良さで、京都試作ネットの会長や京都機械金属中小企業青年連絡会の代表幹事など、幅広いお付き合いもされています。お互いの仕事の話をしながら、刺激を受けつつ公私共に仲が良いので、今回ご紹介させていただきます。
——— 次回は、株式会社名高精工所 代表取締役社長 名高新悟様(1995年同志社大学経済学部卒業)にご登場いただきます!お楽しみに!




.jpg)