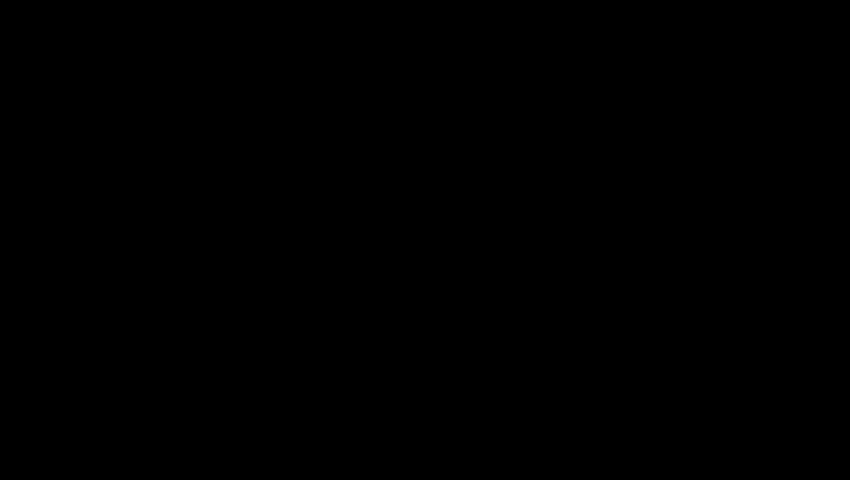同志社人インタビュー第12回 ~漆芸家/Urushi Media 戸田 蓉子さん~
同志社人インタビュー第12回目は、前回の堂上卓也さんにご紹介いただいた、漆芸家/Urushi Media 戸田 蓉子さんにインタビューを行いました。
アトリエを訪問させていただき、貴重なお話を沢山お伺いすることができました。
ぜひ最後までご覧ください!

(アトリエにて)
戸田 蓉子氏 漆芸家/Urushi Media
2003年同志社大学文学部美学芸術学科卒業 大田ゼミ
パリのギャラリーでインターン中に漆に興味をもち帰国後、東京藝術大学名誉教授大西長利氏に漆芸を師事。国際漆展石川金賞、京漆器展理事長賞はじめ受賞多数。ドリームジャパン財団グラント。JapanCraft21クラフトリーダー。アートフェアCollect(ロンドン)、アートフェア東京などに出品し国内外で評価される。
インタビュアー ・同志社女子高等学校1年生 稲澤 万葉(写真:左)
・同志社大学文学部美学芸術学科3年次生 安藤 海伽(写真:右)
Q.(実際の作品を見ながらお話を伺いました。)漆の歴史と戸田さんの作品に込められた思いについて教えてください。
A. 漆はそもそも自分の体を守るために漆の木が出す樹液です。人は縄文時代から漆を使っており、当時は石と木をくっつけるための接着剤であったことが始まりだと言われています。それから人は漆を使って、装飾品や美術品など多くのものを作ってきましたが、元々は自分自身を守るために出している体液ですので、抗菌作用もあり強いものです。酸やアルカリ、有機溶剤にも耐えます。そして、この作品は手紙を容れるカプセルです。漆はその物を守るために塗られてきたという歴史がありますので、「手紙に託された思いを守っていく」という意味を込めています。また、もう相手に届けることのできない、叶わない通信のようなものも入れて、守ってくれたらいいなと思います。タイムカプセルであるかもしれませんね。素地は錫(すず)という金属を使っており、漆は内側にだけ施したものと、外側にだけ施したものがあります。時間と共に変色する錫と、色を変えない漆塗膜が、想いを守る役目を持っています。
Q.もう一つの作品に込められた思いや技法についても教えてください。
A.これは母体の中で赤ちゃんが入っている場所をイメージして、漆の膜がふわっと赤ちゃんを包むように造りました。またこの作品は乾漆という方法で作られています。乾漆とは平安時代に中国から伝わってきた技法、興福寺の阿修羅像など仏像を作るための技法でよくご存じかもしれません。先に粘土や石膏で型を作り、布を貼っていきます。布と、漆と土のペーストのようなものを交互に層にしていくと、カーボンファイバーのような丈夫な構造になります。湿気で割れることもありませんし、非常に軽いので海外に持っていっても大丈夫なんです。
Q.2つの作品を解説していただきましたが、漆を塗る工程で大変なことは何でしょうか。
A.漆の作業は、実は化粧でいうファンデーション作りがほとんどです。素地の上に漆と、土の粉や石の粉をペーストなどにしたものをヘラでつけて、それをまた研いでどんどん平らにする…ということを何回も何回もします。さらにそれを下塗りや中塗りなどを重ねて、徐々に平滑にしていく根気強い作業が必要ですので、それはとても大変ですね。最後のひと塗りのためにも、ひたすら完璧な下地を目指します。
Q.大学生の頃をお聞きしたいのですが、印象的な先生など美学芸術学科での思い出はありますか。
A.日本美術史の先生の講義が印象的でした。その時は東洲斎写楽の講義でしたが、先生曰く写楽の正体って謎だそうです。先生は斎藤十郎兵衛という能役者が正体だと結論付けて多くの論旨を立てていましたが、期末レポートは「あなたが東洲斎写楽になってエッセイを書きなさい」という質問でした。提出前日の夜までどうしようかなと悩んでいましたが、そのまま先生の論を並べるのもどうかと思い、私は写楽を吉原の花魁としてエッセイを書きました。しかも結構楽しみながら。それにはちゃんと論証を書いていましたが、変なこと書いているので点数はないと思っていました。でも、高得点でした(笑)。先生懐広いなと思いつつ、好きなことを好きなように言わせてくれて、受け入れてくれるところがいいなと感じました。
(ルーブル美術館での展示の際のお写真)
(動画作品制作中のお写真)
Q.とてもユニークな先生ですね。美学芸術学科の学びや経験が、今に生きていることは何かありますか。
A.元々、学芸員志望でしたので、言葉で作品について語るっていうことをとても勉強したなと思います。ストーリーやコンセプトを立てることが好きなのは、美学芸術学科の時に「言葉で表すことが楽しい」と感じた経験からだと思います。漆の良さというものを伝える時も、言葉や見せ方など頭を使いながら表現できたらいいですね。私がホームページなどで使うUrushi₋mediaという言葉には、古来からの表現方法で、私の思いを伝えるメディアとしての漆と、漆の美を伝えるメディアとしての私、という意味を込めています。
Q.最後に、戸田さんは漆のどんなところがお好きですか。
A.私は、漆がまだ樹液である状態が最も綺麗で魅力的だと思います。常に平滑をひたすら目指して作業するのですが、結局、究極にスムーズな面ってこの表面張力で張り詰めた液状の状態です。これには養分やエネルギーの塊が入っているように不思議なドロドロの液体で、一番美しいと思うのですが、あまり人の目に止まらないじゃないですか。普段は出来上がりの乾いた状態の漆しか見る機会がないので、見てもらえたらいいなと思い、漆が流れ落ちている映像作品を作りました。もう一つは、漆を刷毛で塗る過程です。実は、漆は人間の髪で作られた刷毛で塗ります。人の髪はコシがあり、強く粘度の高い漆の含みが良い素材なんですよ。そんな髪の刷毛で黒漆をぐっと引くと、艶やかな黒髪を梳かすようにその刷毛から無数の毛の筋がひかれていくようで、それは恐ろしく綺麗だなって思います。
Q.学生へのメッセージをお願いします。
A.漆はかぶれるというように毒も持っています。
私はそれゆえこの素材にひかれます。物事も人間も、さまざまな面を持っているからこそ、深く魅力的なのだと思います。
「ピンからキリのことができる人になりなさい」とまだ20代の頃知り合いの方に言われたことがあります。ピンの部分はまだまだではありますが、そう思って生きてきてみたら、意外と世界は広く楽しいです。
美しいものも醜いものも目を逸らさず見てください。それができる強さは、柔らかな学生時代に持っているものだと思います。そのうち美しいものの中に醜さが、醜いものの中に美しさが見えるかもしれません。混じり合って一つになったり、実は元から一つだったり、その後の展開はあなた次第で、楽しみですね。
インタビューを終えて感想
■安藤 海伽さん(同志社大学文学部美学芸術学科3年次生)
戸田さんの作品に触れて、漆のどこまでも滑らかな手触りに感激しました。しかしどの作品も同じ手触りではなく、若い作品の漆には手から溢れ出るような生命の躍動、自由な動きを持つような感覚を覚え、年季のある漆は手にしっとり張り付くように、長く生きてきた厚みのようなものを感じます。多様に変化する漆の魅力を、作品に触れることで感じるとともに、戸田さんの作り手だけではなく媒介者として漆の魅力を言葉で伝えるお姿に、同じ美学芸術学科生として学ぶものが多くありました。貴重なお話をいただき本当にありがとうございました。
■稲澤 万葉さん(同志社女子高等学校 1年生)
今回のインタビューで、漆についてだけでなく戸田さんの学生時代、これまでどのような経験をされたかということや、私にはない戸田さんの感性や考え方について様々なお話を聞くことができ、良い経験になりました。同じ同志社女子高校出身のお話しをお聞きし、親近感がわくと同時に、好きな道に向かわれる努力や勇気に感動しました。また、実際に漆を塗った作品を触らせていただいて漆の違いを感じることができ、貴重な経験をさせていただくことができました。終始楽しくインタビューをさせていただき、戸田さんのお人柄もとても素敵だと感じました。このインタビューで学べた多くのことを将来の自分に活かしたいと思います。
【戸田さんから次回の同志社人インタビューに登場してくださる方をご紹介いただけないでしょうか。】
何必館・京都現代美術館キュレーターの梶川由紀さんを紹介させていただきます。
梶川由紀さんは、何必館という高い美意識に貫かれた美術館のキュレーターです。そしてここ数年は活躍の領域を工芸にも広げられ、一緒に漆のプロダクトを作らせていただいています。インタビュー時に紹介したカプセル
若い頃からサラ・ムーンやアンリ・カルティエ=ブレッソン、近年ではマイケル・ケンナといった世界的写真家と仕事では対等に渡り合い、プライベートでもそのお人柄から愛されてこられました。気難しい心をも開かせてしまう真っ直ぐな心根と濃やかな気遣い、可憐な外見に隠された芯の強さは、同性の先輩として憧れの同志社人です。
由紀さんと一緒に仕事をすることで、作品を「見せる」ことへの妥協なき美意識を学ばせていただきました。また、由紀さんの中心にある作品への「愛情」と「敬意」ともいうべきもの。由紀さんの手に載った作品が、その瞬間魔法のように光り出すのはそのためだと、私は思っています。
——— 次回は、何必館・京都現代美術館キュレーターの梶川 由紀 様(1992年同志社大学法学部卒業)にご登場いただきます!お楽しみに!