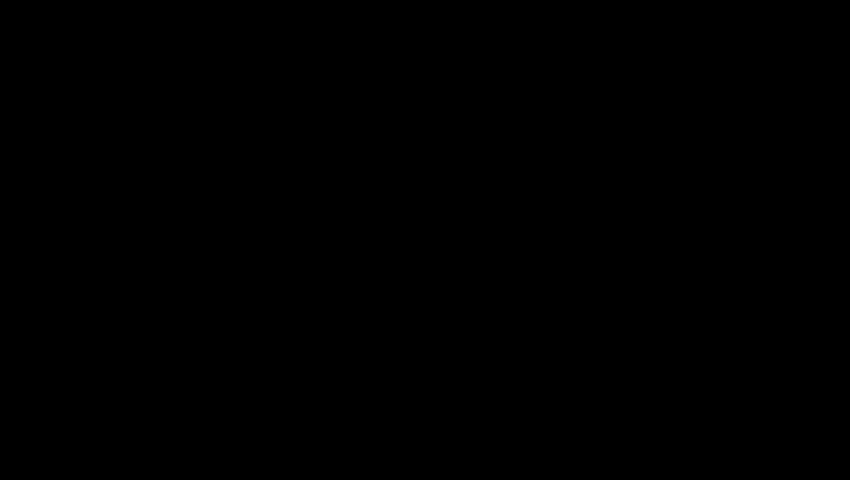同志社人インタビュー第13回 ~何必館・京都現代美術館キュレーター 梶川 由紀さん~
同志社人インタビュー第13回目は、前回の戸田蓉子さんにご紹介いただいた、何必館・京都現代美術館キュレーター 梶川 由紀さんにインタビューを行いました。
何必館・京都現代美術館を訪問させていただき、貴重なお話を沢山お伺いすることができました。
ぜひ最後までご覧ください!
(何必館・京都現代美術館にて)
梶川 由紀氏 何必館・京都現代美術館キュレーター
1992年同志社大学法学部卒業
キュレーターってどんな仕事
インタビュアー ・同志社香里高等学校1年生 永橋 佐彩香(写真:左)
・同志社大学文学部美学芸術学科3年次生 安藤 海伽(写真:右)
Q.キュレーターになると決めたきっかけを教えてください。
A.「芸術家」という存在への好奇心だったと思います。作品はもちろんですが、作品を生み出しているアーティストに興味があります。アーティストがどんな想いで作品を作ってきたのかを知りたいと思いました。実際、キュレーターという肩書きは、アーティストに1歩近づきやすい「幸せのお札」みたいなもので(笑)。アーティストに会ってみたい、知ってみたいという好奇心がきっかけになっています。
Q.キュレーターをしている中でどんな時にやりがいを感じていますか。
A.1つはお客様に「来てよかった」や「見て良かった」と言っていただけるように、鑑賞者に感動を与えることができたときです。ですが、キュレーションや展示はその手助けにすぎないので、もし見に来てくださった方が何かを感じたのであれば、それはその方の手柄だと私は思っています。もう1つは、アートに興味がない方の興味の扉を開くことができたときです。アートへの敷居を下げたり、間口を広げたりすることができたときはやりがいを感じますし、小さな1回の経験が人生の中に積もっていくことで大きな変化になっていくこと、それはとても嬉しいです。
Q.お話の中で、キュレーターはアーティストと鑑賞者の間に立っていると感じました。梶川さんはその双方に対して、大切にしている信条のようなものはありますか。
A.アーティストに対しては、キュレーターとして熱量をもっていたいということ。鑑賞者あるいは社会に対しては、アーティストの思いを届ける優秀なメッセンジャーでいたいということ。キュレーターはアーティストの通訳者であり、伝達者であると考えています。だから、私がフィルターをかけずに、アーティストの人柄、エピソードなど知り得たものを、展覧会において作品と共に鑑賞者へリレーしていけたらと思います。
Q.多くのご経験を培われたからこその大切な信条だと感じます。そんな中、お仕事での失敗談はありますか。また、それをどうやって乗り越えてきましたか。
A.失敗談はもう、笑っちゃうようなことがたくさんあります(笑)。乗り越え方は、失敗も含めて、全部面白がるようにすることです。これは机上の勉強では得られないものかもしれないですね。自分自身の体験―「体解」によって得られるものではないでしょうか。あとは、状況を俯瞰してみて1年後、10年後も同じことで悩んではいないよねって考えること。はたまた、宇宙規模に視点を動かして、自分という存在も時間もほんのチリみたいなものだと考えられた、ふっと気が楽になりますね。
Q.《館内を案内していただきました。》現在(3/30終了)、ロベール・ドアノー(写真家)の展覧会をされていますが、梶川さんが写真を中心的に扱うきっかけや写真という媒体の魅力を教えてください。
A.25歳の時に、パリの写真美術館の設立のための準備室に行ったことがきっかけです。パリの威信をかけて、世界中からよりすぐりのキュレーターやディレクターたちが集結していました。美術館が設立中だったため、会議の合間、倉庫にある貴重な作品を自由に閲覧し、毎日手に取っていく中で写真に魅了されていきました。私が思う写真という媒体の魅力のひとつは、時代に晒されるということだと思っています。カメラという機械を使う以上、フィルムやデジタル、パノラマ、データ保存など、時代によって表現方法が大きく変わる媒体ならではの多様性は面白いと思います。
(フランス・パリ滞在中)
Q.学生時代についてですが、高校または大学時代で最も印象に残っていることは何ですか。
A.大学時代、私は部外連所属のスキー部に入っていて、冬は合宿や試合で雪山にこもって過ごしていました。シーズンオフも京田辺や今出川で陸上トレーニングをして…思い出深いです。そんな学生生活の中心にあったものは友人との信頼関係で、高校・大学に入ってからも幸せな学生時代を過ごしました。そこで培ったコミュニケーション能力は、今の仕事に活きていると思います。人に寄り添ったり、正直に心を開いたり、耳を傾けたりという、嘘ではない人とのつながりを学生時代の人間関係を通して学びました。
Q.素敵な学生生活を過ごされていたのですね。良ければ、今アートに関心を持つ若い人に贈るメッセージを教えてください。
「感じる」ことを大切にしてほしいと思っています。何必館という名前は、「何ぞ、必ずしも?」と定説を疑う自由な精神を忘れたくないという願いをこめた造語です。これはアートの訳でもあります。答えが解るものよりも、自分の中に問いかけを持つこと、自分の感性を磨くものがアートだと考えています。耳を澄ませて感じて、自分のものさしで考えることを大切にしてほしいと思います。
Q.最後に、梶川さんとって同志社とはどのような存在ですか。
A.私が自由に考えること、疑問をもつ余白部分を作ってくれた存在だと思います。多感な10代、20代前半を過ごし、かけがえのない友人と出会わせてくれた場所です。同志社の自由な校風は自分の根っこをつくってくれました。これからも既成概念にとらわれず、のびのびと若者が巣立って行ってくれることを願っています。
インタビューを終えて感想
■安藤 海伽さん(同志社大学文学部美学芸術学科3年次生)
梶川さんへのインタビューを進めていく中で、自分自身のアートに対する考え方を見つめ直すきっかけとなりました。つい作品そのものだけに目を奪われがちですが、アーティストが作品を生み出すまでに歩んできた道のりや込められた想い、その人のアーティスト人生に寄り添えるのは、キュレーターや学芸員だからこそできることだと感じます。多くのアーティストの心を開いてこられた梶川さんの、明るく穏やかなお人柄に触れて、私自身もその世界に飛び込んでみたいという思いが強まりました。残り少ない同志社大学での生活、自分の道を自由に選び取っていきたいと思います。貴重なお話をいただき、本当にありがとうございました。
■永橋 佐彩香さん(同志社香里高等学校 1年生)
私はキュレーターという職業を知らず、インタビューが初めての経験のため緊張していました。しかし、梶川さんの親しみやすい笑顔で緊張がほぐれ、積極的に質問をすることができました。たくさんの興味深いエピソードを話してくださり、ひとつひとつに学びがありました。特に印象に残ったのは「何必」という言葉です。以前から私はアートに対して優劣をつけることに疑問を感じていました。なので梶川さんのお話を受けて私が感じていた疑問がはっきり形になったような感覚がしました。高校生の私にも分かるように言葉を嚙み砕いて伝えてくださったり、ユーモアを交えての話をしてくださったりしてとても楽しいひと時を過ごすことができました。150周年という貴重な機会にこういった経験ができたことに感謝しています。
【梶川さんから次回の同志社人インタビューに登場してくださる方をご紹介いただけないでしょうか。】
株式会社八代目儀兵衛 代表取締役社長の橋本隆志さんをご紹介させていただきます。
橋本さんは大学時代、同じスキー部に所属していました。いつも爽やかな笑顔で、人を惹きつける魅力の持ち主です。
八代目儀兵衛の米料亭が私の美術館からすぐなのでご近所さんの気持ちでおりますが、「お米の美味しさを知ってほしい」という信念を胸に、次々に事業を展開し、めざましいご活躍を遂げていらっしゃいます。
既成概念を打ち破り、お米業界の常識を覆す打ち出し方は見事で、橋本さんの自由な発想と柔軟な対応は、私の思う同志社人のお手本のように思えます。
ビジネスセンスに長けて大成功されておりますが、ブレない志、そして奢ることのない人間性に惹かれている方が大勢いらっしゃることと思います。これからも「米」文化を広げるべく、面白い挑戦をどんどん続けていってほしいと、願っております。
——— 次回は、株式会社八代目儀兵衛 代表取締役社長 橋本 隆志様(1995年同志社大学商学部卒業)にご登場いただきます!お楽しみに!