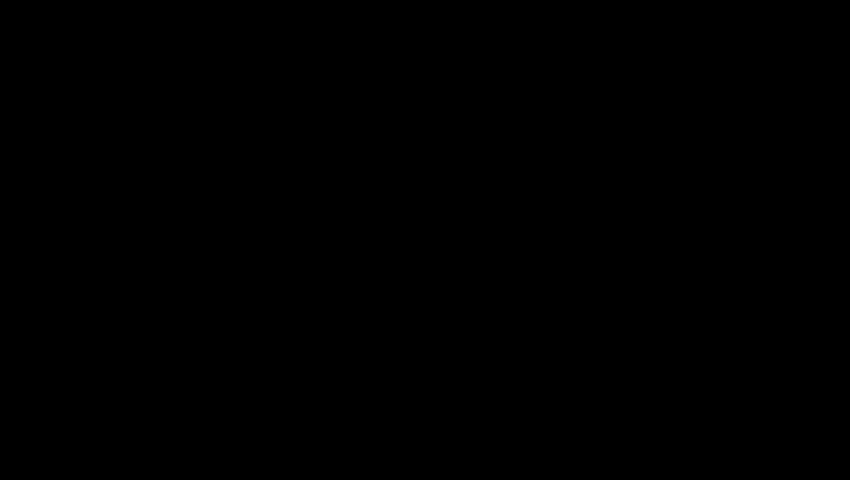会津まつり協賛 学校法⼈同志社創⽴150周年記念講演会
2024年9⽉21⽇(⼟)に会津若松⽂化センターにおいて、創⽴150周年記念講演会を開催しました。講師は同志社⼥⼦⼤学名誉教授の吉海直⼈⽒、講演テーマは、「⼋重が結んだ会津若松と同志社」でした。吉海先生は講演に際して、以下のことをコメントされておられました。
「同志社において、⼋重は新島襄の妻として知られているが、会津出⾝であることはあまり重視されなかった。ところが⼋重の周辺には会津藩出⾝者がたくさん集まっている。それは兄の覚⾺が就職を斡旋していたからであろう。そのことは京都会津会の会報にも反映されている。定期的に⿊⾕の⻄雲院で会合を持っており、それは現在でも継続されている。⼤河ドラマ「⼋重の桜」によって会津若松と同志社の交流が⾏われたが、放映から10年経過すると、あまり熱⼼には⾏われなくなったように思える。せっかく⼋重が結んでくれたのだから、同志社は会津のことを、会津は同志社のことをもっとよく知って、活発な交流が望まれる。」
講演の様子、講師の吉海名誉教授
当日司会を担当した同志社大学生の佐藤ソフィアさんから講演を聴いた感想を寄せてもらいました。佐藤さんは地元の会津若松ザベリオ学園高等学校の出身です。
司会の同志社大学1年佐藤ソフィアさん
また、講演に先立ち、吉海先生により会津若松ザベリオ学園高等学校の高校1年生を対象とした新島八重・山本覚馬ゆかりの地を巡るバスツアーを行いました。吉海先生のガイドにより、二人の生涯や業績についてより深く学ぶことができました。
(訪問先)
大龍寺内 山本家の墓碑
福島県立博物館内 新島八重の銅像
山本覚馬・新島八重 生誕の地碑(歌碑)
鶴ヶ城(車窓見学)
日本基督教団会津若松教会
大龍寺山本家墓所にて
~感想~ 同志社大学文学部文化史学科1年次生 佐藤ソフィア
八重の桜が大河ドラマになった後に、同志社大学に眠っていた史料が出てきた事で、様々な事が明らかになった。一つとして、八重は男勝りでハッキリしている性格である事もあり、夫である襄を敬愛する者たちからは悪妻と呼ばれていた。そんな八重とその兄である覚馬について講演を聴いて考えてみた。
同志社大学の創立者である新島襄と会津出身の新島八重という関係性だけでなく、会津若松と京都の縁を繋ぐ為にも、会津では、新島八重顕彰会を立ち上げ、八重の命日である6月14日に毎年、大龍寺の住職がお経をあげた後に、賛美歌を歌うという仏教とキリスト教を交えた法要を行っている。昭和5年に大龍寺に建てられた山本家の石碑が今では、観光名所になっている。しかし、八重のお墓は京都の若王子にある事を前提に置いておかなければならない。八重の桜の影響で、新島旧邸には、100年分の観光客が訪れたとも言われているが、八重だけでなく、兄の山本覚馬にも視点を当てると、覚馬は、目が見えず足も使えない状態でありながらも、京都が戊辰戦争で焼け野原になった時、京都府顧問として、その当時の復興を担った事を注視したい。また、会津藩が逃げそびれて薩摩藩に幽閉された場所(かつて覚馬が下屋敷としていた)に現在の同志社大学がある。これまで、同志社大学の元である同志社英学校は新島襄の熱意によって設立されたとされているが、新島襄1人の力でできたものではなく、宣教師であるデイヴィスと八重の兄である山本覚馬の3人の尽力によるものである。山本覚馬の書いた『管見(かんけん)』の中に、学校を作り、日本人に教養を身につけさせ、国際人を育てるという内容が書かれており、それに加えて女学を与える事もこれからは必要であると記されていた。覚馬自身にも女学校を作りたいという意志があったのである。その後も、京都は山本覚馬の設計した通りに復興策が実践されていった。その一例として、琵琶湖疏水が挙げられる。山本覚馬が会津の事を頭に置き、設計を考えていたとしたら、会津と京都が結びついている可能性もあり得る。
また、覚馬は国際化の為に京都博覧会を開催し、フリーパスで外国人が誰でも入れるようにし、その結果、聖書に触れることになった。キリスト教を学んでいた兄の影響により八重が英語で聖書を学んでいた宣教師のところに襄が訪れて、八重と出会ったのである。
覚馬は、議会が始まると府議会議員の初代議長になる。そして、功労者でもあった事から京都商工会議所の会頭になり、最終的には同志社大学の臨時総長にまでなった。
八重に関しては、歴史的背景から、会津人として九州の薩摩・長州の人々に対してあまり寛容でなかったが、襄の晩年近くのことであるが八重が家に薩摩出身の生徒を呼び、かるた大会をやった事に襄が歓喜したと記されている。百人一首というものは、方言では書かれないはずであったが、会津には板かるたが存在していた。しかし、史料が残っていなかった事から北海道で下の句板かるたが文化遺産に登録された。その後になって、会津でも江戸時代の板かるたが会津で出てきた。よって、現在、福島県立博物館に板かるたが展示されている。八重自身も板かるたをしていた事が明らかにされている。
このように、八重だけでなく、兄である山本覚馬も同志社に貢献していたという事実から深い繋がりがある事が分かる。また、新島八重・山本覚馬だけでなく、会津と京都の繋がりについても理解が深まった。特に、襄と覚馬とデイヴィスの3人が尽力し協力し合いながら創り上げられた同志社大学に通えているという事は、会津出身の身からすると誇らしく感じられた。